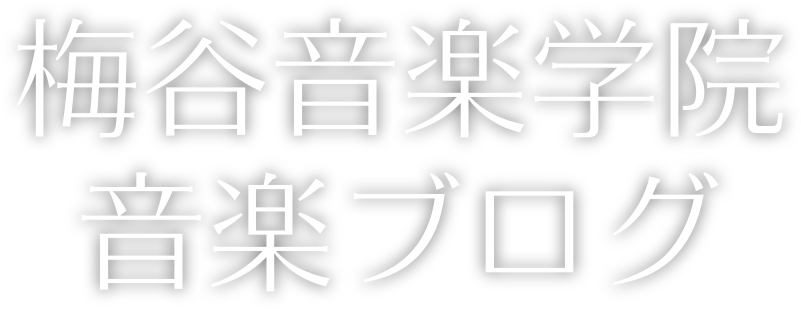「♪ あし~た は~まべ~を さま~よ~えば~ ♪ 」
日本を代表する愛唱歌として長く歌いつがれている『浜辺の歌』。
皆さんも、一度は、歌ったことがあるでしょう。
作られたのは、何と、大正時代の1916(大正5)年です。
100年以上も前に作られた、
軽やかでなめらかな美しいメロディは、今なお多くの人々に親しまれています。
『浜辺の歌』のメロディが、
聴く人の心に心地良く染み込むわけは、どこにあるのでしょうか。
曲が作られた背景や内容を知ることで、歌の表現に活かしましょう。
🎼学校音楽の教材として
第二次世界大戦が1945(昭和20)年に終結し、
戦後、音楽も含めた日本の学校教育の、質の向上が求められている中で、
『浜辺の歌』は、
1947(昭和22)年に、中学校の音楽教科書に掲載され、
1977(昭和52)年には、
中学校学習指導要綱において、「夏の思い出」「早春賦」と並んで、
2年生の【共通教材】に指定されました。
以来、平成の時代に至るまで、教科書に掲載され続け、
日本の情緒あふれる風景や、
日本人の心情を学ぶ良質な教材として、
少年少女の情操教育の役割を、担い続けました。
▼【共通教材】の目的は
日本の文化を継承し、世代を超えて同じ歌を共有し歌い継ぐこと。
🎼【日本の歌百選】に認定
国民全体に広く浸透し、深く愛されてきた『浜辺の歌』は、
日本を代表する歌として、
2006年に【日本の歌百選】に選ばれています。
▼【日本の歌百選】とは
2006年に、文化庁と日本PTA全国協議会が、
親子で長く歌い継いでほしい抒情歌・愛唱歌を、101曲選んだもの。
「100」ではなく「101」曲なのは、
選考の結果、どうしてもしぼり切れなかったため。
🎼【日本の歌シリーズ郵便切手】発行
『浜辺の歌』は、1979(昭和54)年から9回に渡って発行された
【日本の歌シリーズ郵便切手(全18曲)】に選ばれています。
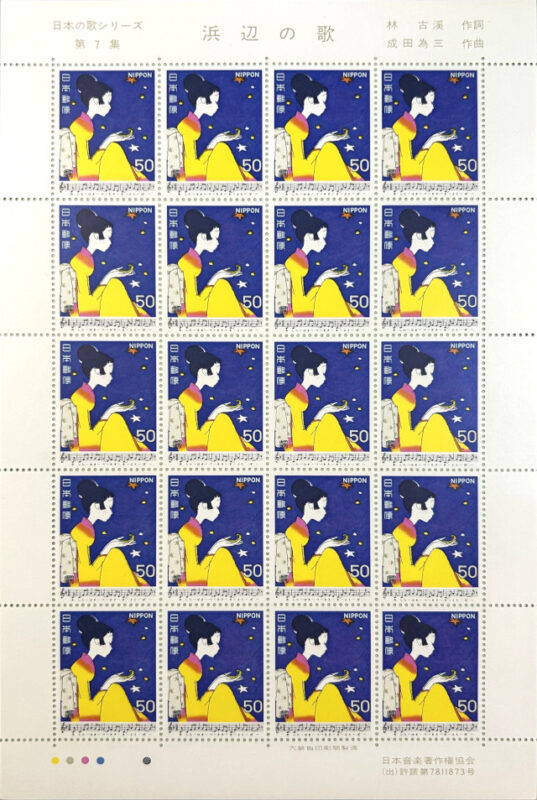
▼【日本の歌シリーズ郵便切手】とは
「このシリーズは、日本人の心の歌として、
古くから多くの人に歌い継がれてきた歌の中から18曲を選び、
これらの歌の持つイメージを絵に表現し、
我が国 初の音楽切手として発行するものです。
・・・・・
選曲に当たっては、小学校及び中学校の新学習指導要綱の
共通教材とされている26曲の中から、各2学年2曲ずつ18曲を選びました。
・・・・・」
郵政省発行:「日本の歌シリーズ切手スタンプ帳」より
🎼『浜辺の歌』原詩の作詞者
『浜辺の歌』原詩の作詞者は、
林 古渓(はやし こけい)
1875(明治8)年 – 1947(昭和22)年
歌人、作詞家、教育者(立教大学教授)です。
🎼『浜辺の歌』原詩はひらがな表記
林 古渓 作詞『浜辺の歌』の原詩は、
1913(大正2)年、
東京音楽学校(現在の東京藝術大学)学友会が発行する、
雑誌『音楽』に発表されました。
実は、原詩の題名は、『浜辺の歌』ではなく、
『はまべ』です。
詩は、全3節ありますが、
その中で、漢字で表記されている言葉は、わずかに単語2つで、
他は全て、ひらがなで書かれています。
🎹ひらがな表記のわけ
林 古渓が、2語の他は全て、
ひらがな表記にしたわけは何でしょうか。
ひらがなの特徴から考えてみましょう。
▼ひらがなの特徴
特徴①
視覚的に、丸く優しい表現となり、親しみやすい。
特徴②
平安時代に発展した日本独自の文字であり、
日本特有の情緒的な心情表現を的確に表現することができた。
日本独自の文字【ひらがな】がまだなかった時代は、
中国から伝来した漢字のみを用いていたが、
漢字だけでは、日本語の意味の全てを正確に表すことができなかったため、
ひらがなの前身【万葉仮名】が作られ、さらに【ひらがな】に発展した。
ひらがなの特徴①②から、
古渓は、より【日本的なイメージ】を強調するために、
ひらがな表記にしたのではないでしょうか。
『浜辺の歌』の作曲者は、
原詩を尊重し、『はまべ』を題名として作曲しています。
※作曲者については後述します。
それにもかかわらず、
1918(大正7)年、出版された楽譜の題名は、
『浜辺の歌』に改題されており、
歌詞の多くは、ひらがなではなく、漢字表記に変えられていました。
当時は、著作権などの作者の権利が曖昧な時代で、
出版社側が、ひらがなと漢字を合わせた一般的な文の方が読みやすい、
と判断し、古渓の許可なく、変えてしまったのです。
🎼『浜辺の歌』原詩の意味&解説
🎹『浜辺の歌』知られざる第3節にこそ意味がある
1947年(昭和22年)に、
『浜辺の歌』が中学校の音楽教科書に掲載された際にもまた、
作詞者 林 古渓の意向ではないことが、行われています。
それは、第3節は、中学生には難しい内容だと判断されたため、
教科書には、第2節までの掲載となったことです。
そのため、一般的には、
第3節が存在することが、広く知られていません。
ですが、
掲載されなかった第3節の歌詞にこそ、
『浜辺の歌』の重要な意味が書かれているのです。
🎹『浜辺の歌』原詩&意味:第1、2節
まず、第1、2節では、
何について書かれているのか、
原詩『はまべ』の言葉の意味を確認しながら、みていきましょう。
原詩『はまべ』
①
あした はまべを さまよへば、
むかしの ことぞ しのばるる。
かぜの おとよ、くもの さまよ。
よするなみも かひの いろも。
②
ゆふべ はまべを もとおれば、
むかしの ひとぞ しのばるる。
よする なみよ、かへす なみよ。
つきのいろも ほしの かげも。
①
あした・・朝 「明日」ではありません。
しのばるる・・懐かしく思い出す
かひ・・貝
②
ゆふべ・・夕方
もとおれば・・散策する、徘徊する
①
朝の浜辺をあてもなく歩いていると、
昔のことが懐かしく思い出される。
風の音、雲の様子、
寄せる波、貝の色からも。
②
夕べの浜辺をふらりと散歩していると、
昔の人が懐かしく思い出される。
寄せる波、返す波、
月の色、星の光からも。
第1、2節だけを読むと、
《 浜辺をゆるりと散策し、美しい自然に触れて、
心穏やかに、昔の思い出や昔の友人を懐かしく思い出している 》
ように感じられます。
🎹『浜辺の歌』原詩&意味:知られざる第3節
では、
教科書に掲載される際に、省かれてしまった第3節には、
いったい何が書かれているのでしょうか。
同じように、言葉の意味を確認しながら、みていきましょう。
③
はやち たちまち なみを ふき、
赤裳の すそぞ ぬれもひぢし。
やみし われは すでにいえて、
はまべの眞砂(まさご) まなご いまは。
はやち・・疾風(はやて)急に激しく吹く風
赤裳(あかも)・・女性用の赤い着物
眞砂(まさご)・・白いさらさらの砂
まなご・・愛する女性もしくは子ども
急に強い風が吹いて 大きな波がたち、
着物の裾が すっかり濡れてしまった。
病んでいた私は もう癒えて、
きれいな砂の上、愛するあなたは今は。
このままでは、意味がわかりにくいですね。
〈行間部分〉を付け足して、意味がつながるように、意訳してみます。
⇩
急に強い風が吹いて 大きな波がたち、
〈あなたの〉着物の裾が すっかり濡れてしまった。
〈それからあなたは去ってしまった。〉
※時間的経過があったと推測されます。
病んでいた私は もう癒えて、
きれいな砂の上〈を歩いているとあなたが思い出される〉、
愛するあなたは、今は〈もういない〉。
▼【今は〈もういない〉】と意訳する理由は
【しのばるる】が使われているからです。
意味は、
【遠く離れた人、亡くなった人、過去の出来事を懐かしく思い出す】なので、
今は、側にはいないのです。
第3節で、
《 愛するあなたは、今は〈もういない〉。》
と書かれていることにより、
第1、2節の意味も大きく変わってきます。
ただ単に、
《 浜辺をゆるりと散策し、美しい自然に触れて、
心穏やかに、昔の思い出や昔の友人を懐かしく思い出している 》
のではないことがわかります。
第1、2節の
【今はもういなくなってしまった過去に愛した大切な人】
【今はもういない愛する人との大切な思い出】
を歌っていることがわかります。
そして、
【今はいない愛する人との大切な思い出】のひとつが、
第3節に書かれている、
【急に強い風が吹いて 大きな波がたち、
あなたの着物の裾が すっかり濡れてしまった。】
であり、
第1、2節で書かれている歌詞の意味は、
《 昔、愛するあなたと一緒に歩いた、思い出深い浜辺を、
今、ひとりであてもなくさまよい歩いていると、
あなたとの大切な思い出を懐かしく思い出します。》
と、なるのです。
🎹『浜辺の歌』原詩は日本の文化そのものを表している
原詩『はまべ』は、
林 古渓の故郷、神奈川県藤沢市の辻堂東海岸を思い浮かべながら、
書かれたと言われています。
※辻堂駅の発車メロディに採用されました。(2016年~)
原詩『はまべ』が表しているのは、
人が、時代を超えて普遍的に持つ心情です。
その心情とは、
《 生まれ育った故郷への愛着や旅愁 》
《 過ぎ去った過去に対する憂いや懐かしさ 》
《 失った愛する人を、いつまでも切なく思い慕う気持ち 》
です。さらに、この心情は、
①
風の音、雲の様子、寄せる波、貝の色からも
②
寄せる波、返す波、月の色、星の光からも
と、歌詞に書かれているように、
様々な自然に触れると同時に呼び起こされています。
これは、
《 情緒あふれる美しい自然との調和、
移り行く不完全なものの中にある、美や儚さ(はかなさ)への共感 》
など、日本人特有の美意識といわれる心情を表しています。
原詩『はまべ』は、
《 日本人の心の文化そのもの 》
を表しているのです。
🎼『浜辺の歌』作曲者について
『浜辺の歌』作曲者は、
成田為三(なりたためぞう)
1893(明治26)-1945(昭和20)年
作曲家、教育者(現在の国立音楽大学教授)です。
🎹『浜辺の歌』はデビュー作にして代表作
1916(大正5)年
東京音楽学校(現在の東京藝術大学)在学中に、
古渓の原詩『はまべ』に曲を付け、
1918(大正7)年
音楽出版社が『浜辺の歌』と改題して出版。
これがデビュー作となりました。
1918(大正7)年
《 芸術性の高い文学・音楽を子供たちに届ける 》
という理念のもとに刊行された、
児童のための雑誌『赤い鳥』の専属作曲家となり、
多くの童謡を作曲しました。
『赤い鳥』刊行以前は、
歌唱曲であっても、詩だけが掲載され、楽譜部分は省かれていました。
『浜辺の歌』は、『赤い鳥』の理念のもと、
楽譜付きで掲載された、初の歌唱曲となりました。
▼児童のための雑誌『赤い鳥』とは
1918(大正7)年、
鈴木三重吉
(1882(明治15)-1936(昭和11)小説家・児童文学者)
が創刊した童話と童謡の児童雑誌。
芸術性豊かな童話や童謡が掲載され、
日本の近代児童文学が飛躍的に発展しました。
また、【童謡】という言葉が、日本で初めて使われ、
童謡の普及にも大きく貢献しました。
『赤い鳥』創刊日の7月1日は、【童謡の日】に制定されています。
参加した主な芸術家
芥川龍之介、北原白秋・山田耕作など、当時の代表的な作家・音楽家が参加した。
以来、100年以上もの間、
歌い続けられている名歌『浜辺の歌』は、
為三のデビュー作にして、代表作となりました。
🎹西洋音楽を日本に広めた成田為三
♬音楽理論に長けた本格的な作曲家
成田為三は、1922(大正11)年 28歳の時に、
4年間ベルリンに留学し、
和声学、対位法、作曲法、ピアノ、指揮法を習得しました。
帰国後は、
東京高等音楽院(現国立音楽大学)などで教師をしながら、
歌曲、管弦楽曲、ピアノ曲などを作曲しました。
その数は、300曲あまりにもなります。
ドイツで習得した【対位法】は、
当時の日本では、先進的な作曲論でした。
成田為三は、
〈西洋音楽を日本に広めたい〉
という熱意を持って、作曲に取り組み、
作曲の他、『対位法』『和声学』などの著作も手がけるなど、
音楽理論に長けた本格的な作曲家でした。
ですが、
1945(昭和20)年の東京大空襲で、
管弦楽やピアノ曲の楽譜の多くが失われてしまい、
歌曲や童謡の作曲家として知られるにとどまっていました。
その後、弟子たちによる研究が進められ、
現在では、為三が、日本の音楽史に果たした役割の大きさが、再確認されつつあります。
🎼『浜辺の歌』は日本の音楽史上、重要な歌曲
為三は、『浜辺の歌』を、
【唱歌】という教育のための規範曲から離れ、
より自由な発想で作曲しました。
西洋の音楽を積極的に取り入れながらも、
日本人の繊細な情感を歌う、芸術性の高い歌曲を作り上げたのです。
🎹大正ロマンの風潮にのって
為三が活躍した大正時代(1912-1926年)は、
【大正ロマン】と呼ばれる新しい文化が生まれた時代です。
▼大正ロマンとは
特徴①和洋折衷
西洋文化が広がる中、日本の伝統的な美意識も尊重され、
和と洋が融合した新しいスタイルが生まれた。
特徴②ロマン主義
個人の感情や個性を尊重する芸術作品が積極的に作られた。
特徴③自由主義
大正デモクラシー(自由を重視することを主張した社会運動)による
自由なテーマ、価値観の作品が作られた。
大正ロマンに活躍した代表的な芸術家
竹久夢二・与謝野晶子・谷崎潤一郎・芥川龍之介・山田耕作
和洋折衷の新しい文化が花開く【大正ロマン】の風潮にのって、
為三のデビュー作『浜辺の歌』は、
発表当時から大きな話題作となり、
現在では、
《 新しい時代を切り拓いた歌曲 》
として、日本音楽史の上で、重要な歌曲と言われています。
🎼『浜辺の歌』特徴&解説
では、為三は、
『浜辺の歌』に、西洋音楽の要素をどのように取り入れたのか、
歌曲としての魅力をみていきましょう。
🎹『浜辺の歌』はヨーロッパ由来の6/8拍子
『浜辺の歌』の最大の特徴は、
6/8拍子で作られていることです。
日本の唱歌・童謡や、現代のJポップに至るまでも、歌唱曲は、
4/4拍子の曲が圧倒的に多くなっています。
4拍子が、日本古来のリズムだからです。
6/8拍子は、ヨーロッパ由来のリズムであり、
ヨーロッパの伝統音楽、ダンス音楽に広く用いられています。
※詳しく知りたい方は、
ブログ記事「『カントリーロード』で聴き比べ、日本語と英語のリズム感の違い:歌のレッスン」
をご覧ください。
今回の記事の終わりにリンクがあります。
▼6/8拍子とは
1小節に8分音符が6つあり、
それが、3 + 3 の2つの3連符が組み合わさったようなリズム感になる。
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ = ♪ ♪ ♪ + ♪ ♪ ♪
特徴①
8分音符の細かい動きで、流れるような感じを表すことができる。
特徴②
大きくは2つのまとまりに聞こえるため、
8分音符の細かい動きにも関わらず、不思議にゆったりとした印象になる。
{ 1 } { 2 }
♪ ♪ ♪ + ♪ ♪ ♪
⇩
特徴①②ともに、
『波』を表すリズムとして、最適です。
歌のメロディー、ピアノ伴奏のどちらにも、
寄せては返す波の動きが、優美になめらかに表現されていて、
耳に心地よく余韻を残します。
🎹ウィーン発祥のウィンナワルツ風に
為三は、『浜辺の歌』を、
19世紀のウィーンで流行し、その後、世界的に広まった
【ウィンナワルツ】を参考にして作曲しました。
▼ウィンナワルツとは
ヨハン・シュトラウス1世が発展させ、
息子の2世が完成させた。
2世はウインナワルツの黄金時代を築き、【ワルツ王】と呼ばれる。
特徴①
3/4または3/8拍子
3拍子が均等ではなく、2拍目をやや早めにずらして演奏することで、
独特の軽快な流動感を生む。
特徴②
リズム・和声などの構成が、ある程度の決まりの上に作曲される。
⇩
聴く人に安心感を与え、
特定の層だけではなく、広く一般的に受け入れられる大衆的な娯楽性を備えている。
代表曲
『美しく青きドナウ』『皇帝円舞曲』『ウィーンの森の物語』『南国のばら』など
ウインナワルツの要素を取り入れて作曲された『浜辺の歌』は、
優雅で軽快、躍動感にあふれつつも、
不思議と穏やかで落ち着いた心地良さが感じられるメロディです。
※ウインナワルツを参考にしながらも、
基本である3/4または3/8拍子ではなく、6/8拍子で作曲したわけ
3拍子は、日本人にとって馴染みがないため、
{ 1 } { 2 }
♪ ♪ ♪ + ♪ ♪ ♪
3拍子が2つ繰り返されて、大きく2拍子に聞こえる6/8拍子を用い、
日本人に馴染みやすくしたと考えられます。
🎼『浜辺の歌』は《見事なまでに和と洋が調和》した歌曲
『浜辺の歌』は、
人が、時代を超えて普遍的に持つ、
《 故郷への愛着・過去に対する憂いや懐かしさ・大切な人を思い慕う気持ち 》
を、様々な自然描写を通して、
日本人特有の美意識といわれる、
《 日本的心情:
情緒あふれる美しい自然との調和、
移り行く不完全なものの中にある美や、儚さ(はかなさ)への共感 》
を呼び起こす詩と、
西洋発祥の ウィンナワルツの要素を取り入れ、
《 ヨハン・シュトラウス的:
優美で躍動感あふれつつも穏やかでなめらかな 》メロディが、
《 寄せては返す波 》となって、さらに深く心に染みわたり、
いつまでも心地良い余韻となって穏やかに優しく心に響く、
《 見事なまでに、和と洋が調和 》した、
《 新しい時代の象徴となった楽曲 》
なのです。
歌 / 野々村綾乃
♬ 知られざる第3節も録画されているので、是非、お聴きください。
🎼『浜辺の歌』をご一緒に歌いませんか
『浜辺の歌』を、当教室の声楽のレッスンで歌いませんか。
ご一緒に、心地良く豊かな時間を過ごしましょう!
※日本人のリズム感について、詳しく知りたい方は、
こちらのブログ記事「『カントリーロード』で聴き比べ、日本語と英語のリズム感の違い:歌のレッスン」
を、是非、ご覧ください。
🎼~音楽資料紹介~
🎹自筆譜ファクシミリ版:ヨハン・シュトラウス2世作曲『美しく青きドナウ』
成田為三が『浜辺の歌』の作曲に参考にしたウインナワルツのうち、
世界的に最も有名な曲、
ヨハン・シュトラウス2世作曲『美しく青きドナウ』(ピアノ版)
についての資料をご紹介させていただきます。
自筆譜ファクシミリ版
ヨハン・シュトラウス2世作曲『美しく青きドナウ』(ピアノ版)
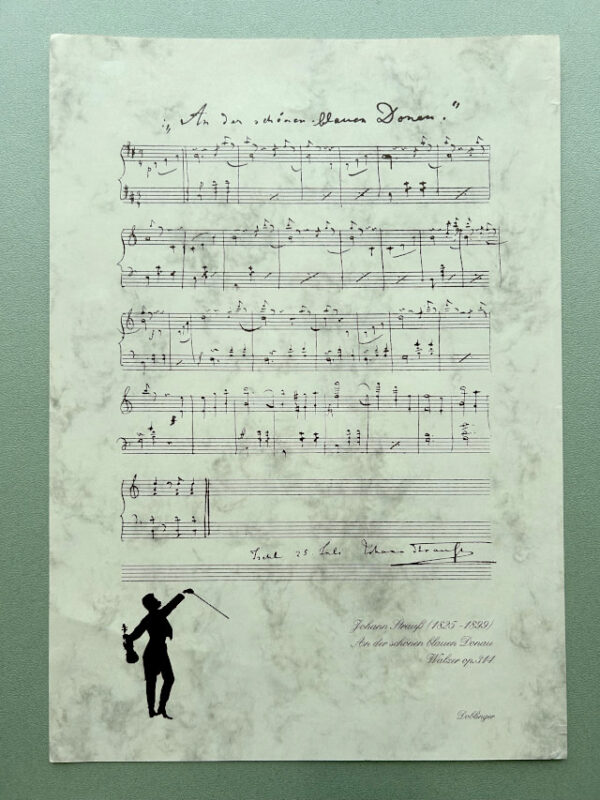
※シュトラウス一家と親交、その出版に成功。
梅谷音楽学院~展示資料より
▼ヨハン・シュトラウス2世
(1825-1899年 オーストリア 作曲家・指揮者)
父であるヨハン・シュトラウス1世が作った、
ウインナワルツの基盤を受け継ぎ、その黄金時代を築きあげました。
【ワルツ王】として世界的に有名で、
特にウィーンでは、「もうひとりの皇帝」とまで呼ばれ、崇められています。
華やかで明るい曲想、優美なメロディが特徴。
ヨハン・シュトラウス2世作曲の3大ワルツ
『美しく青きドナウ』『皇帝円舞曲』『ウィーンの森の物語』
▼『美しく青きドナウ』
1867年 ヨハン・シュトラウス2世作曲。
ウインナワルツの代名詞と言われ、オーストリアの第2の国歌として愛されています。
▼ファクシミリ版とは
歴史的価値を持つ自筆譜や初版楽譜などを、
正確・忠実に複写・複製して再現し、出版された版。
今回のコラムにお付き合いいただきありがとうございました。
次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も
よろしくお願いいたします。
梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪