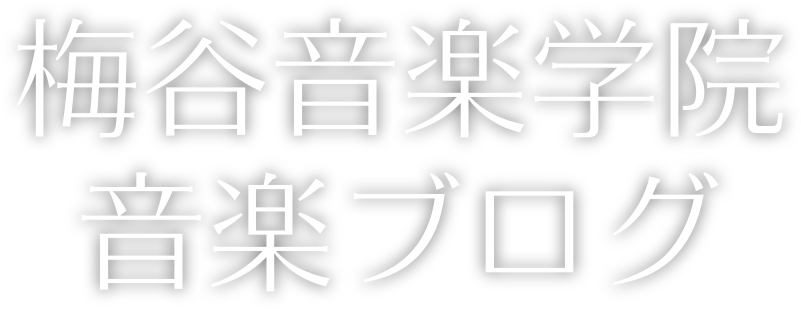🎼「ベートーヴェン の三大ピアノソナタ」のひとつ
ベートーヴェンピアノソナタ第8番ハ短調 Op.13『悲愴』は、
ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ全32曲の中でも、特に名高いソナタです。
第14番『月光』第23番『熱情』と合わせて、
「ベートーヴェン の三大ピアノソナタ」と呼ばれ、
ピアノを学ぶ人ならば、
誰もが必ず弾いてみたいと願う憧れの曲で、
当教室でも、レッスンしています。
珍しいのは、
いかにもベートーヴェン!の
激しく情熱的な1楽章や、憂いが漂う軽快なリズムと、厳かなハーモニーが、
交互に緩急変化する3楽章よりも、
一般的には、
2楽章のメロディーが良く知られています。
柔らかで、うっとりするような美しいメロディーが、
今までに何度も、有名企業のテレビCMに使用されています。
今回は、
『悲愴』ソナタが作曲された背景を知り、理解を深めることで、
より深みのある感情表現につなげていきましょう。
その前に、
ベートーヴェンの作品の中でも、交響曲と並んで意義深いとされる、
【ピアノソナタ】全般について、学んでいきましょう。
🎼ベートーヴェンにとってのピアノソナタの意義とは
ベートーヴェンにとって【ピアノソナタ】は、
自身の音楽を革新的に発展させ、
表現することができる重要な作品でした。
ベートーヴェンは、生涯、
【ピアノソナタ】を世の中に送り出すことに、情熱を注ぎ続けました。
🎹鍵盤楽器が、歴史上、最も大きく発展した時期
ちょうど、ベートーヴェンが作曲家として
活躍し始めたころから、
まるで、ベートーヴェンの
燃える創作意欲に合わせるかのように、
鍵盤楽器が飛躍的に発展していきました。
▼鍵盤楽器の発展の歴史
♬18世紀前半まで
ピアノの前身楽器「ハープシコード」
音の強弱なし
音域3~5オクターブ
♬18世紀初め(1709年)
初代ピアノ「ピアノ・エ・フォルテ」の発明
ハンマーアクションを備える
⇩
その名の通り、
音の強弱がタッチにより可能になる
♬18世紀後半にかけて
音域5オクターブ半まで広がる
♬19世紀はじめ~
☆鍵盤楽器が、歴史上、最も大きく発展した時期☆
ペダルやハンマーアクションの
さらなる進歩
新しい素材のフレームや弦の発明
⇩
強い音(フォルテ)の連続が、
安定して出せるようになる
音域7オクターブまで広がる
19世紀はじめは、
ピアノは、高度な演奏技術に耐えられる高性能なものに改良され、
楽曲の表現の幅が、画期的に広がっていました。
ちょうど、
ベートーヴェンが作曲家として認められ始めた時期に当たり、
進化したピアノの機能を最大限まで生かした【ピアノソナタ】を
次々に生み出していくことが、
ベートーヴェン自身の音楽を革新的に発展させ、
表現することになったのです。
🎼ベートーヴェンの音楽とは、どのような音楽なのでしょうか。
では、
ベートーヴェンの音楽とは、どのような音楽なのでしょうか。
主に、次の3つの点があげられます。
🎹 ① ひとりの人間としての魂の発露、それが音楽
ベートーヴェンよりも前に活躍した
ハイドン、モーツァルトたち音楽家は、
貴族に雇われて、
貴族が娯楽として楽しむための曲を作っていました。
そのため、雇い主の貴族たちが喜ぶような、
明るく華やかな、軽やかな音楽が求められ、
自己表現としての音楽を作曲し、
演奏できる機会は与えられていませんでした。
ベートーヴェンも、
若いころに宮廷に仕えていましたが、
《自由に曲を作りたい!》
と強く望んでいました。
ベートーヴェンの思いと呼応するかのように、
フランス革命(1789-1795年:18世紀終わりころ)が起き、
貴族社会が崩壊していきます。
まさに、歴史の転換期の只中に、ベートーヴェンがいたのです。
《これからは、貴族が求める曲ではなく、自由に曲が作れる!》
ベートーヴェンは、
ひとりの人間としての様々な感情を、
曲に注ぎ込んで作曲し、才能を開花させていきます。
ベートーヴェンにとって音楽とは、
自己表現のためにありました。
湧き上がってくるひとりの人間としての魂の発露
それが、ベートーヴェンの音楽なのです。
※ベートーヴェンには、ほぼ生涯に渡って資金面で支えてくれた貴族たちがいました。
それは、ベートーヴェンの音楽に敬意を表し、音楽の振興に熱心な貴族たちでした。
そのため、ベートーヴェンは、自由に、自分自身の感情を表現した曲を作曲できたのです。
一方、モーツァルトは、宮廷音楽家として仕えていた大司教と25歳の時に決裂し、
その後、独立しました。フリーで生計を立てた初めての音楽家がモーツァルトです。
しかし、収入を得るためには、裕福な貴族にピアノを教えたり、貴族の邸宅を借りての演奏会など、
貴族が気に入る音楽から逸脱することは、難しいことでした。
🎹 ② 音楽史上で最も重要な革新となった、新しい音楽作品の数々
ベートーヴェンの魂の叫びから生み出し続けられた、数々の音楽作品は、
【 クラシック音楽史上で最も重要な革新】
と言われています。
ベートーヴェンは、
クラシック音楽の歴史における、
古典派と呼ばれる時代(18世紀中ごろ〜19世紀はじめ)の作曲家です。
古典派の音楽は、先人として、
この時代に活躍した偉大な音楽家、
ハイドンとモーツァルトが確立した音楽様式がありました。
しかし、ベートーヴェンは、
フランス革命という時代の転換期の波に乗り、
古典派の音楽様式にとらわれず、
自由な発想で、
心にあふれ出てくる感情を表現するために、
独自の音楽を築き上げていきます。
魂が求めるままに作曲することで、
既存の音楽の様式を変えていきました。
確立された様式・形式に基づいた曲ではなく、
誰も聴いたことがないような斬新で、
劇的に展開していく音楽を、次々に作曲したのです。
作品のひとつひとつが、
個性にあふれ、創造性に満ち、強いエネルギーを放ち、
聴いた人だれもが驚嘆しました。
そして今もなお、人々の心を揺さぶり続けるのです。
ベートーヴェンの音楽は、
【 クラシック音楽史上で最も重要な革新】となり、
次の時代のロマン派音楽へとつながっていったのです。
🎹 ③ 音楽は、 貴族のためではない、民衆のために!
フランス革命が起こり、
貴族中心の社会から民衆の社会への転換期の中で、
ベートーヴェンは、貴族の娯楽のための音楽ではなく、
民衆のために音楽を作曲しました。
裕福に優雅に暮らしていた貴族たちとは違い、
貧しい生活の苦しみの中から、
自由と平等を求めて立ち上がった民衆たちの姿が、自分自身と重なったのです。
自分を鼓舞するための音楽は、
同時に、民衆を勇気づけるための音楽でした。
《困難に立ち向かおう!苦しみを乗り越えて、
進もう!その先には喜びがある!》
自分と民衆のための音楽を作曲すること
は、ベートーヴェン自身が、
人生の苦しみを乗り越えていくための使命感となりました。
心の中に湧き上がる情熱を使命感に変えて、
自分自身と民衆を救おうとしたのが、ベートーヴェンの音楽です。
🎼まさにミラクル!神に選ばれたベートーヴェン
【 クラシック音楽史上で最も重要な革新】となった、
新しい音楽作品の数々が生み出された背景には、
【奇跡的】に重なった、3つの事柄があるのです。
2つは、これまでにお話した、
大きな歴史的できごとと、
もうひとつは、ベートーヴェンに背負わされた運命です。
🎹2つの大きな歴史的できごとは【偶然】か【必然】か
❶ピアノの飛躍的な発展
❷フランス革命による貴族社会の崩壊
この2つの大きな歴史的できごとは、
《ひとりの人間として、自由に、
自己表現のために、
そして、民衆のために音楽を作りたい!》
という、ベートーヴェンの強い意志に合わせるかのように起こり、
ベートーヴェンの創作に重要な役割を持つことになりました。
これは、【偶然】なのでしょうか。
強いエネルギー同士が、お互いが必要とするものを引き寄せ、合わさり、
さらにエネルギーを増した大きなパワーによって、
それぞれが急速に変化、飛躍的に進化していったように感じられます。
これは、【偶然】ではなく、
【必然】に起こるべくして起こったのではないでしょうか。
🎹【奇跡】というべき、もうひとつのできごと
➌ ベートーヴェンを襲った《 難聴 》
もし、
ベートーヴェンが、音楽家として致命的な
《 難聴 》という苦悩を抱えることがなかったとしたら、
【 クラシック音楽史上で最も重要な革新】となるほどの数々の作品は、
生まれていたのでしょうか。
ベートーヴェンは、自身が抱えた
強烈な苦悩や不安、恐怖、
そして、その先に見た歓び・・・
湧き上がってくるひとりの人間としての
激しい感情を情熱に変えて、作品として昇華していきました。
ベートーヴェンにとって、
苦悩はエネルギーの源だったのです。
そのエネルギーが強ければ強いほど、
音楽に宿るエネルギーは強くなり、
今もなお、消えることなく光を放ち続け、
世界中の人々の魂を揺さぶり続けているのです。
《大きな時代の転換期に、
それが起きている場所に、
大きな苦悩を抱えたベートーヴェンが、
作曲家として存在していた》
これは、まさに、
【奇跡】ではないでしょうか!
ベートーヴェンは、神に選ばれたのです!
🎼『悲愴』は、ベートーヴェンピアノソナタの前期作品の頂点
ベートーヴェンにとって【ピアノソナタ】は、
自身の音楽を革新的に発展させ、表現することができる重要な作品で、
全32作品が作曲されました。
作曲された時期や作風によって、前期、中期、後期に分けられています。
※時期については、いくつかの考え方により違いがありますが、便宜上のものです。
ここでは、1800年までに作曲された第11番までを前期作品とします。
ピアノソナタ第8番ハ短調 Op.13『悲愴』は
《前期11作品の中の頂点》と言われる曲で、
ピアニストとして活躍していたベートーヴェンが、
作曲家として世の人々に認められることになった重要な作品です。
ダニエル・バレンボイム 演奏
ベートーヴェンピアノソナタ32曲の全曲を5回も!!!録音している巨匠の名演奏です!
まさに、
《傑作》と言われている『悲愴』ソナタは、
どのような作品なのでしょうか。
《前期11作品の中の頂点》と言われるわけについては、
次のブログを、是非、ご覧ください。
ベートーヴェンが作曲した、
名曲ばかりがズラリと並ぶピアノソナタの中でも、
特に、『悲愴』ソナタが《傑作》と言われている背景を知り、理解を深めることで、
より深みのある感情表現につなげていきましょう。
今回のコラムにもお付き合いいただき、
ありがとうございました。
次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も
よろしくお願いします。
梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪