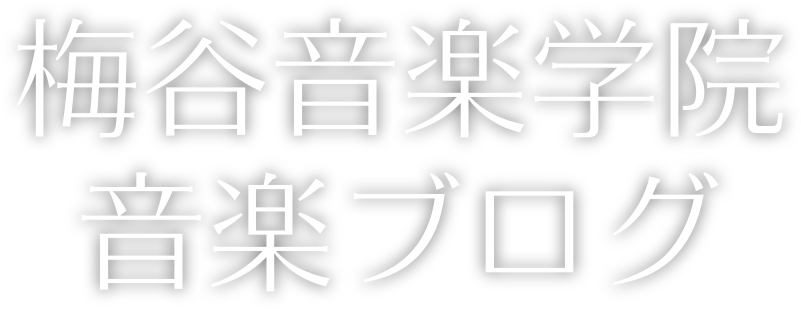🎼『戦場のメリークリスマス』は《死》と《生》と表す
「戦場」と「メリークリスマス」が合わされたネーミングは、
そのネーミングだけで、心がハッとするような強い印象が残ります。
「戦場」は《死》を、
「メリークリスマス」は《生》を表しているからでしょう。
どちらも、人の根源的な感情を呼び覚ます言葉です。
当音楽教室のピアノ科でレッスンしている
『戦場のメリークリスマス』。
心が洗われるような心地の良いメロディーは、
どのように生みだされたのでしょうか。
『戦場のメリークリスマス』が作曲された背景を知ることで、
演奏の表現を、より深めていきましょう。
この曲は、
映画『戦場のメリークリスマス』のために作曲されました。
まずは、映画について簡単にご紹介します。
🎼映画『戦場のメリークリスマス』
『戦場のメリークリスマス』は、
本来は、1983年5月に公開された、
日英豪ニュージーランド合作の、映画のタイトルです。
監督は、
カンヌ国際映画祭 最優秀監督賞 受賞の経歴を持ち、国際的に高い評価を得ていた、
大島渚 監督(1932(昭和7)年-2013(平成25)年)です。
🎹映画『戦場のメリークリスマス』のテーマ
映画の内容は、
第二次世界大戦下のジャワ島を舞台に、
日本軍兵士と、
日本軍の捕虜となっている連合軍兵士の、
東洋と西洋の価値観や習慣の違いがぶつかり合い、お互いに、とまどいながらも、
不思議なことに、次第に惹かれ合っていき、
友情が生まれます。
その後、日本が敗戦国となり、
日本軍兵士と、連合軍兵士の立場が逆転します。
お互いの間に生まれた友情は、変わらずに保たれるでしょうか。
大島渚監督の、
監督人生の生涯のテーマが、
「極限状態での人と人のつながり」
でした。
『戦場のメリークリスマス』は、まさに、
大島渚監督の、生涯のテーマそのものを描いた映画です。
🎹異色の映画『戦場のメリークリスマス』
映画『戦場のメリークリスマス』は、
様々な点で、異色の作品だと言えます。
①戦争映画ですが、戦闘シーンは一切ありません。
②主要な出演者は、全て男性です。
③配役に、当時は俳優ではなかった人、
または、本業は俳優ではなかった人を多く選んでいます。
坂本龍一 / 日本軍のエリート士官役
(ミュージシャン)
ビートたけし / 日本軍軍曹
(お笑い芸人)
デヴィッド・ボウイ / 連合軍少佐
(世界的に有名なイギリスのロックアーティスト )
ジョニー大倉 / 朝鮮人軍属
(ミュージシャン)
内田裕也 / 拘禁所長
(ミュージシャン)
三上寛 / 憲兵中尉
(ミュージシャン)
🎼映画『戦場のメリークリスマス』のメインテーマ曲
映画『戦場のメリークリスマス』のメインテーマ曲は、
「英国アカデミー賞作曲賞」(1984)を受賞し、世界的に有名になった曲で、
皆さんも、耳にしたことがあるでしょう。
穏やかで静寂なメロディーが、
深く深く心の内面にしみ込んでいき、
優しい愛で包まれているような陶酔感を抱きます。
そして、
自分自身と世界との境界がなくなり、
溶け合っているような感覚に引き込まれていきます。
この名曲は、映画のタイトルと同じく、
『戦場のメリークリスマス』と呼ばれていますが、
正しい曲名は、
『Merry Christmas, Mr.Lawrence』
(メリークリスマス ミスターローレンス)
です。
🎼「Merry Christmas, Mr.Lawrence」(メリークリスマス ミスターローレンス)の意味
「ミスターローレンス」とは、
日本軍の捕虜となっている連合軍ロレンス中佐のことです。
ビートたけし扮する日本軍ハラ軍曹との間に、次第に友情が芽生えます。
映画の中で、
日本軍ハラ軍曹が、捕虜のロレンス中佐に、
「Merry Christmas, Mr.Lawrence」
(メリークリスマス ミスターローレンス)
と、声をかける場面が2回あります。
捕虜のロレンス中佐が、
ある理由で独房に入れられていたのを、
ハラ軍曹の独断で開放するとき。
その夜は、クリスマスでした。
映画の最後の場面です。
終戦後、ハラは、
敗戦国戦犯として処刑されるのを待つ身となります。
監獄に訪ねてきたロレンスと、
クリスマスの夜のことを思い出し、笑い合った後に、
ロレンスが去っていくとき。
「Merry Christmas, Mr.Lawrence」
(メリークリスマス ミスターローレンス)
の一文は、
映画『戦場のメリークリスマス』のテーマ
「極限状態での人と人のつながり」で生まれた
友情と親愛の証を表す言葉
なのです。
「Merry Christmas, Mr.Lawrence」
(メリークリスマス ミスターローレンス)
は、そのまま、映画のテーマ曲の題名として、付けられました。
🎼『戦場のメリークリスマス』の作曲者は坂本龍一さん
「Merry Christmas, Mr.Lawrence」
(メリークリスマス ミスターローレンス)
を含めて、
映画『戦場のメリークリスマス』の音楽を作りあげたのは、
日本を代表する音楽家で、世界的にも著名な
坂本龍一さん(1952年-2023年)です。
作曲家、ピアニスト、プロデューサーとして多方面で活躍しました。
坂本龍一さんは、この作品で、
「英国アカデミー賞作曲賞」(1984)を、
日本人で初めて受賞したのを皮切りに、
映画「ラストエンペラー」では、
アカデミーオリジナル音楽作曲賞(1988)
※日本人初
グラミー賞(1989)
ゴールデングローブ賞(1988)
映画「シェルタリング・スカイ」では、
ゴールデングローブ作曲賞(1991)
など、映画・音楽界の権威ある賞を数々受賞、
輝かしい活躍をなさいました。
また、
音楽活動だけではなく、
環境問題や人権問題にも積極的に関わり、
森林保全団体の設立、
音楽活動を通しての、脱原発、地震被災地支援などを行いました。
日本が世界に誇る音楽家の坂本龍一さんは、
2023年3月に、癌のため、お亡くなりになりました。
ご冥福をお祈りいたします。
🎼『戦場のメリークリスマス』の音楽的な価値&意味
※曲名の『メリークリスマス ミスターローレンス』ですが、
ここでは、一般的に知られている曲名である
『戦場のメリークリスマス』を使って、お話を続けます。
世界的に広く有名になった
『戦場のメリークリスマス』は、
それまでの音楽に対する価値を一変させたと言われています。
『戦場のメリークリスマス』が、
音楽全般に与えた影響について、考えていきましょう。
🎹シンセサイザーによる革新的なサウンド
テーマ曲『戦場のメリークリスマス』は、
シンセサイザーという電子楽器で演奏されています。
▼電子楽器シンセサイザーとは
電子工学的な手法で、
音を合成し、自在に音色を作成できる鍵盤楽器。
演奏だけではなく、編集やレコーディングにも使われる。
「合成する」を英語で「synthesize:シンセサイズ」という。
テクノロジーの発展により、
シンセサイザーが発明され、世の中に流通したことが、
音楽そのものを劇的に変化させました。
それは、
《音楽が成り立つ条件の劇的な変化》
です。
基本的に、主に3つの要素で音楽が作られています。
これを【音楽の3大要素】といいます。
※細かく言えば、多くの要素があります。
⇩
メロディー(旋律)
ハーモニー(和声)
リズム(拍子)
音楽は、これら3つの要素が合わさることで出来ています。
シンセサイザーが登場したことによって、
この【音楽の3大要素】に、
サウンド(音色)
の要素を加えて、音楽を構成する必要が出てきたのです。
この《サウンド(音色)》とは、
ピアノのタッチや、ヴァイオリンの弓の動かし方など、
演奏者の演奏技術によって音色を変えるのではなく、
《音を合成し、自在に音色を作成する》
という意味です。
坂本さんは、
この《音楽が成り立つ条件の劇的な変化》について、
「作曲の仕事が机上で譜面を前にしただけではできなくなった。」
と表現しています。
『戦場のメリークリスマス』は、
音楽の新たな要素である
《サウンド(音色)》を
《自在に合成して》作曲された
革新的・斬新的な音楽でした。
🎹シンセサイザーの合成音は人の心を揺さぶるか
人は、自然界の生き物である以上、
本来は、自然の法則に従って生きることで、
心身ともに健康でいられるため、
【自然でないもの】を、拒否する傾向にあります。
ですから、
【電子的なもの】を耳にすると、不快に感じるのが、ごく普通です。
坂本龍一さんと親交のあった、
音楽プロデューサーの小室哲哉さんは、
坂本さんについて、次のように評しています。
「教授(坂本さんのニックネーム)は、
シンセサイザーで人の心を動かすことができた。
この楽器を使って人の心を揺さぶるのは奇跡に近い。
その奇跡を何度も起こしていた。」
坂本さんは、
この《奇跡に近い》音楽『戦場のメリークリスマス』を、
どのようにして生みだしたのでしょうか。
🎹テーマ曲『戦場のメリークリスマス』に込められた思い
テーマ曲『戦場のメリークリスマス』は、
ゆったりと流れる穏やかなメロディーと、
大地が息づいているようにリズムを刻み、
森の木々や、動物たちの営みまでもが脳裏に浮かんでくるイメージで、
ゆらゆらゆらいでいるエネルギーを感じます。
地球の奥深くに流れるエネルギーが、
静かに、そして厳かに、伝わってくるのです。
このメロディーは、
日本の童謡・演歌などに使われている
東洋的な音階と、
西洋の古典音楽の基本的なメロディー進行とを、合わせて作られているので、
【東洋と西洋の融合】の音楽を作りだした、
と高い評価を得ました。
ですが、坂本さんは、
【東洋と西洋の融合】ではなく、
【東洋から見ても、西洋から見ても、どこでもないどこか】
を表すと同時に、
【古代であり、現代であり、いつでもない時間】
を表現した、と語っています。
🎹《【どこでもないどこか・ いつでもない時間】の音楽》の意味
【どこでもないどこか・ いつでもない時間】
の音楽とは、具体的には、どのような音楽のことでしょうか。
【どこ・いつ】を特定しないためには、
何か特定のこと、ものをイメージさせないこと、です。
また、どこで聴いても、いつ聴いても、
【その場所、その時】を表している音楽でなければなりません。
坂本さんは、
テーマ曲『戦場のメリークリスマス』の音を、
ほぼシンセサイザーのみで作り出しています。
坂本さんが、シンセサイザーで作り出した《サウンド(音色)》は、
《人間の根源的なもの》
つまり、
《生・死・宇宙・地球・自然》
を連想させます。
地球のエネルギーのような大きな何かを感じるのです。
《人間の根源的なもの》
《生・死・宇宙・地球・自然》
⇩
【どこでもないどこか・ いつでもない時間】
全てに共通して、存在します。
テーマ曲『戦場のメリークリスマス』を聴いて、胸を打たれるのは、
《私たちが、もと居た場所、いつか帰る場所》
を思い起こす音楽だからではないでしょうか。
坂本龍一さんが目指した
【どこでもないどこか・ いつでもない時間】
の音楽は、
シンセサイザーだからこそ、
《人間の根源的なもの》を連想させる《サウンド(音色)》を、
作り出すことが可能だった、とも言えます。
(メリークリスマス ミスターローレンス)
オリジナルサウンドトラック
作曲・演奏 / 坂本龍一
🎼ピアノで【どこでもないどこか・ いつでもない時間】を表現してみましょう。
シンセサイザーの自在な音で作りだされた
『戦場のメリークリスマス』を、
当教室でご一緒に、ピアノで表現してみませんか。
ピアノは、
電子楽器のシンセサイザーとは違って、
演奏者の技術や気持ちが、そのまま伝わり、
《音色》として表現されます。
【どこでもないどこか・ いつでもない時間】
の音楽を、ご自身の《音色》で奏でて、
心地良い時間を味わいましょう。
(メリークリスマス ミスターローレンス)
“Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022″より
坂本龍一さんご本人の、最期の演奏です。
闘病中の、全身全霊での演奏は、心揺さぶられます。
今回のコラムにもお付き合いいただき、
ありがとうございました。
次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も
よろしくお願いします。
梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪