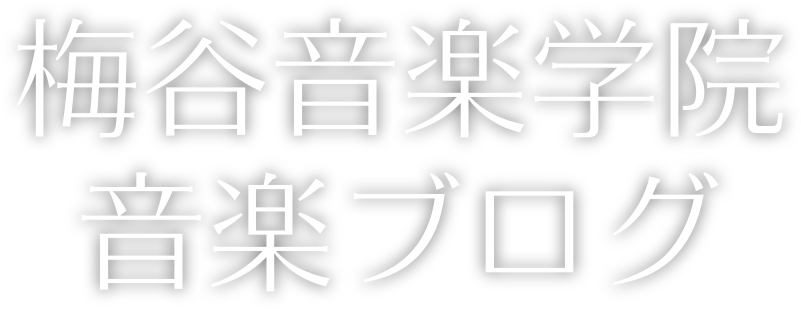ベートーヴェン作曲のピアノソナタ
全32曲の中でも、
三大ピアノソナタのうちのひとつとして有名な
『ピアノソナタ第14番 月光』は、
『苦悩を挑戦に変える曲!』と、
私の中で名付けることにしました。
前回のコラム『まぼろしの月だった?』
の中では、『ピアノソナタ第14番』の
『月光』という題名は、ベートーヴェン自身が
付けたのではなかった!!!
という大変ショッキングなことをお話しました。
詳しくは、前回のコラムを是非、お読みください。
※コラムの最後にリンクがあります。
今回は、その続きです。
ベートーヴェン自身が「月光」をイメージしたのではないのなら、
いったい何を主題(テーマ)にして、
あの幽玄なメロディーが、生み出されたのでしょうか?
知りたくなりますね。ですが、残念ながら、
ベートーヴェンが何を思って作曲したのかは、
誰にもわからないのです。
身分違いの女性へのかなわぬ恋心、という説や、
盲目の少女のためにピアノを弾くことで月の光を表現した、という説、、、
(この説は、いかにも本当のことのように、
教科書に載っていたこともありますが、
現在では、完全な作り話だと明らかになっています。)
このような様々な逸話は残っていますが、
信憑性のあるものは、ひとつもありません。
前回にも書いたように、
音楽評論家であり詩人であった
ルートヴィヒ・レルシュタープ(1799-1860)が、このソナタを
「湖の月光の波に揺らぐ小舟のよう」と評したことから、
通称『月光ソナタ』と呼ばれるようになりました。
また、10才から3年間ベートーヴェンの弟子として指導を受け、
ピアノ練習曲集でもおなじみの
カール・チェルニー(ツェルニー)(1791-1857)は、
「夜景、遥か彼方から魂の悲しげな声が聞こえる」と評しています。
「月光」という先入観がなければ、
皆さんなら、何を思い浮かべるでしょうか?
ベートーヴェンが何を思って
『ピアノソナタ第14番』を作曲したのか、
当時のベートーヴェンのおかれた状況から、
私の心に感じるイメージをふくらませてみて、
思いを巡らせてみました。
そして、たどり着いた主題(テーマ)が、
『苦悩を挑戦に変える曲!』です。
なぜ、そう思うのかを、これからお話していきます。
『ピアノソナタ第14番』は、
一度でも聴いたり弾いたりしてみれば、
ベートーヴェンが何を思って作曲したのか、
誰でも知りたくなるような
畏敬と驚嘆の気持ちがわいてくるようなメロディーです。
心がおおきく震えてくるのです!
実は、このソナタには、『月光』ではなく、
ベートーヴェン自身が付けた副題があります。
『幻想曲風ソナタ』といいます。
「幻想曲」とは、「即興や自由な発想の曲」
を意味する言葉です。
ベートーヴェンは、これまでの伝統的な
古典音楽の常識から離れて、自由な発想で、
新しい音楽を作ろうとしていました。
『ピアノソナタ第14番』に
『幻想曲風ソナタ』と副題を付けることで、
「新しい音楽を作曲することに挑戦した強い意志」
を人々に伝えたかったのだと考えられます。
実際に聴いてみると、すぐ後のロマン派音楽の
先駆けのような作品になっています。
何と!当時、常識だったピアノソナタの形式を使っていません!
※第3楽章はソナタ形式です。
形式を大切に作曲されていた当時としては、
まさに異彩を放つソナタ!!!を作曲し、
その斬新さに人々は驚嘆しました。
ソナタ形式とは? ~簡単な解説~ ・主に古典音楽で使われた音楽の形式。 例えば、ポップスで、 Aメロ→Bメロ→サビ、 と 決まった形式があるのと同じ。 ・交響曲やソナタに用いられた。 ・提示部・展開部・再現部 の 3つの部分に分かれている。 ①提示部 主題(テーマ)を2つ提示する。 ②展開部 主題を、転調(キーを変える)したり、 リズムやハーモニーを変える、など アレンジして盛り上げる。 ➂再現部 始めの調子(キー)に戻り、 2つの主題がより親密になって しめくくる。 ★ソナタ形式で、 曲の最初に提示された主題は、 ①~➂の間ずっと繰り返し流れていることになるため、 その曲のイメージ、キャラクターを決める もっとも重要なフレーズとなります。 言いかえれば、ソナタ形式は 作曲者のイメージする主題を 曲の始まりから終わりまで効果的に盛り上げて表現することで、 より強く作曲者の思いを伝えることができる形式なのです。
そこで、ベートーヴェン『ピアノソナタ第14番 月光』はというと、、
【第1楽章】
何と!ソナタ形式をとっていません!!
始まりから終わりまで一貫して
遅くゆるやかに 音を保って
(Adagio sostenuto)で演奏されます。
さらに、「常に可能な限り小さい音で繊細に」
という、ベートーヴェン自身の指示が書き込まれています。
速いテンポで、大きい音も積極的に使った
ソナタ形式が用いられることが
一般的だったので、人々を驚かせるような
第1楽章となりました。
曲が始まるとすぐに、
神秘的幻想的な空間の中に吸い込まれ、
厳粛な気持ちがわいてきます。
「無」の世界から音が降りてくるような感覚になる第1楽章は、
このソナタの他にはないでしょう。
・
・
さて、ここで少し、
このソナタを作曲した31歳の頃のベートーヴェンについてお話すると、
患っていた難聴が悪化し始め、
作曲家としての将来に暗雲が立ち込めてきた頃でした。
ベートーヴェンは、
自分自身の不幸な境遇を乗り越えようとして、
あえて強い意志を持って
「新しい音楽を作曲することに挑戦した」
そして、その意志の表明として『ピアノソナタ第14番』に
『幻想曲風ソナタ』と副題を付けたのではないでしょうか。
・
・
そのような状況におかれたベートーヴェンに
思いをはせると、
曲の始まりから続く左手の3連符は
「不安にさいなまれて揺れるベートーヴェン自身の心」
右手の符点音符のメロディーは
「ベートーヴェン自身の悲痛な叫び」に聞こえてきます。
ベートーヴェン自身の抑圧された苦悩や不安や嘆きが、
そのまま主題(テーマ)に込められていると感じます。
ベートーヴェン ピアノソナタ第14番『月光』第1楽章から再生されます。
ベートーヴェンピアノソナタ32曲の全曲を5回も!!!録音している巨匠の名演奏です!
【第2楽章】
第1、第3楽章の極めて挑戦的な楽章の間に、
明るく可憐なメロディーが効果的に使われています。
ベートーヴェンが、
つかの間、苦悩から解放されて、
軽い足取りで森の中を散策している姿を思わせるメロディーは、
美しい花々、緑濃く茂る木々、元気な鳥の鳴き声に
癒されていくベートーヴェンの心のようです。
ベートーヴェン ピアノソナタ第14番『月光』第2楽章から再生されます。
指揮者にしてピアニストでもある巨匠の色彩豊かで叙情的な名演奏です。
【第3楽章】
いきなりアルペジオの連続で一気に音階を駆け上がり、
叩きつけるような激しい和音を響かせ、
心がかき乱されるようなメロディーが次々と絡み合います。
終始 、
急速に激しくせき込んで( Presto agitato)演奏するため、
ただならぬ緊張感で追い込まれ、
神経が麻痺したように高ぶります。
第1楽章の抑圧されたベートーヴェンの苦悩や不安や嘆きが、
この第3楽章で、これでもか!!!
というくらいに怒りのような激情となって、
ほとばしっています。
苦悩を打ち砕き、不安を払いのけ、嘆きを原動力とし、
新しい音楽を生みだすんだ!
とベートーヴェン自身が叫んでいるように
聞こえてきます。
ベートーヴェン ピアノソナタ第14番『月光』第3楽章から再生されます。
激しさだけではない、ベートーヴェンへの敬愛が感じられる深く豊かな表現をお聞きください。指揮者にしてピアニストでもある巨匠の名演奏です。
このようなことから、
ベートーヴェン『ピアノソナタ第14番 月光』を
私の中では『苦悩を挑戦に変える曲!』
と名付けることにしました。
ぜひ、皆さんも、聴いたり弾いたりして、
おおきく感動してみてください。
すると、この時のベートーヴェンが乗り移った?!みたいに
「苦悩を打ち砕き、不安を払いのけ、嘆きを原動力とし、
挑戦していく勇気がわいてくる!!!」
かもしれません。
・・・長いお話にお付き合いいただいて、ありがとうございました!
次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も
よろしくお願いします。
梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪
🎼関連コラムのご紹介
前回のコラム『まぼろしの月だった?』は、
『ピアノソナタ第14番』の
『月光』という題名は、ベートーヴェン自身が付けたのではなかった!!!
では、いったい誰が、いつ、名付けたのでしょうか?というお話です。
ご興味のある方は、是非、お読みください。
コラム「『悲愴』ソナタ:神に選ばれたベートーヴェンのミラクル!ピアノレッスン」では、
ベートーヴェンの音楽が、
【 クラシック音楽史上で最も重要な革新】となったわけと、
ベートーヴェンが生涯、情熱を注ぎ続けて、
数々の新しい独創的な、独自の音楽作品を生み出した背景に、
【奇跡的】に重なった、3つの事柄についてお話しています。
ご興味のある方は、是非、こちらもご覧ください。
コラム「『悲愴』ベートーヴェン革新的作曲家誕生のソナタ」では、
ベートーヴェンにとって【ピアノソナタ】は、
自身の音楽を革新的に発展させ、表現することができる重要な作品でした。
ベートーヴェンが作曲した、
名曲ばかりがズラリと並ぶピアノソナタの中でも、
特に、『悲愴』ソナタが《前期11作品の中の頂点》と言われているわけについて、お話しています。
ご興味のある方は、是非、こちらもご覧ください。