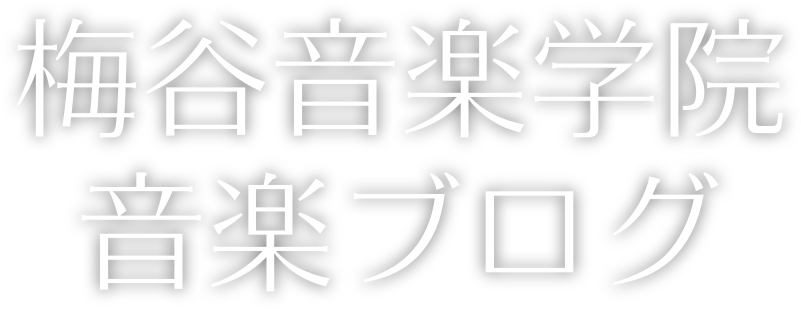🎼『初恋』は難しくも美しい【日本歌曲】を代表する名曲
当教室の、
大人の声楽科クラスでレッスンしている
【日本歌曲】『初恋』は、声楽家が好んで歌う名曲です。
【日本歌曲】は、《 表現すること 》が、全般的に難しい、と言えますが、
その中でも『初恋』は、
特に豊かな表現力が求められる、情緒豊かな曲です。
【日本歌曲】とは、
【日本語の詩に曲を付けた歌】のことですが、
日本人が、母国語の歌を歌うのに、
なぜ、難しいのでしょうか。
その理由は、
母国語である日本語が難しいからです。
※詳しくは、前回のコラム
「『初恋』日本文化の美意識の結晶!表現豊かに歌う:歌のレッスン」を、
是非、ご覧ください。終わりにリンクがあります。
🎼詩と音楽の融合【日本歌曲】を表現豊かに歌うためには
【日本歌曲】とは、
【日本語の詩に曲を付けた歌】のことではあるのですが、
単に、それだけではありません。
【日本歌曲】とは、
《 詩に曲を付け、
詩の内容を歌で表現することで、詩と音楽が融合し、
より一層、高度な芸術作品となった曲 》
のことです。
ですから、
【日本歌曲】を歌うためには、
まず、歌詞を読んで、
作詞者の心情・感情を、敏感に感じ取ることが大切です。
日本語は、
日本人の《 和の精神 》からもたらされる
繊細な感受性、美意識を表す独特の言葉として、
感覚的表現の言葉になりました。
《 感覚として、感じ取らなければならない 》のが日本語です。
そして、詩の内容を歌で表現するために、
歌うときにも、
詩の情緒豊かさと同じだけの、
繊細な感受性、美意識を十分に表現する力が求められます。
🎼日本歌曲『初恋』の作詞者について
作詞者は、
特に抒情性の高いすぐれた詩を詠んだ
名高い歌人・詩人として知られている
石川啄木(1886(明治19)年-1912(明治45)年 岩手県)です。
16歳の時に、
文学で身を立てようと決意しましたが、
経済的に成功できず、
幾度も病を繰り返します。
病と生活苦にあえぎながら、
多方面で作品を執筆し続けますが、
1912(明治45)年、
26歳の若さでこの世を去ってしまいました。
🎼日本歌曲『初恋』の歌詞&現代語訳
『初恋』は、
石川啄木が亡くなる2年前、
1910(明治43)年に刊行された、
啄木の第1歌集『一握の砂』の中の短歌です。
啄木の故郷への郷愁の思い、
成功できずにいる苦しみ、
家族を亡くした哀しみなどが詠まれています。
『初恋』だけを単独の短歌として読むと、
純粋に、甘く切ない「初恋の思い出」を歌っているかのように感じます。
ですが、
啄木の短かすぎる作家人生の背景を知ると、
『初恋』は、単に、
「初恋の思い出」の歌ではないことがわかります。
では、
啄木が詠んだ短歌『初恋』と、
現代語訳も合わせて読んでみましょう。
砂山の砂に腹這(はらば)ひ
初恋の
いたみを遠くおもい出づる日
砂山の砂に腹ばいとなり、
ふと初恋の痛みを遠い日の思い出として
思い返す今日という日よ
この短歌が単独の作品だとすると、
若者の、みずみずしい「初恋の思い出」として詠まれた、
という解釈が成り立つように思われます。
ですが、
『初恋』は、単独で詠まれたのではなく、
歌集『一握の砂』の、一連の歌の中に組み込まれています。
歌集『一握の砂』は、
生涯、病と生活苦に悩み悶えた啄木の、
自己憐憫や死生観などを詠んだ歌が、
ズラリと並んでいるのです。
その一連の中に詠まれている短歌『初恋』は、
どんな意味をもっているのでしょうか。
さらに、内容を深堀りしてみましょう。
🎼短歌『初恋』の内容を深堀り!歌の表現に活かしましょう
🎹「砂」という言葉で表現されているのは
カギとなるのは、「砂」という言葉です。
歌集の題名『一握の「砂」』の、
そのままの意味は、
「ほんのわずかな一握りの砂」です。
そこに、
啄木のどんな思いが込められているのでしょうか。
歌集『一握の砂』の、
《巻頭》の歌から続けて10首は、
「砂浜」に関連した内容になっています。
そのうちの、
実に9首に「砂」という言葉が使われています。
『初恋』は、
《巻頭》の歌から数えて6首目で、
「砂山の砂に」と始まります。
《巻頭》の歌は、
歌集の印象を決定づける大切な役割がありますから、
《巻頭》から続けて9首もの歌に、
「砂」という言葉を並べて使っていることから、
啄木にとって、
「砂」という言葉は、重要な意味を持っている、ということがわかります。
「砂」は、
啄木の心の内面をうつし出すために選んだ言葉だと言えます。
🎹歌集『一握の砂』の巻頭から10首の現代語訳&解釈
「砂」という言葉で表現されている、
啄木の心の内面を知るために、
歌集『一握の砂』の、
巻頭から10首の現代語訳を読んでみましょう。
※スペースの都合で元の短歌は省略しました。
①東海の
小鳥の磯の「白砂」に
私は泣きぬれて
カニとたわむれる
②頬につたう涙もぬぐわずに
私は「一握の砂」を
示した人を忘れない
③大海に向かって一人
七日八日と泣いてやろうとして
家を出てしまった
※「砂」という言葉はないですが、「砂浜」に関連した内容です。
④ひどく錆びたピストルが出た
「砂山の砂」を指でもって
掘っていたときに
⑤ある一晩に
嵐が来て築いたこの「砂山」は
何の墓かなあ
⑥※『初恋』
「砂山の砂」に腹這い
初恋のいたみを遠く
思い出す日
⑦「砂山」の裾に横たわっている流木に
あたりを見回して
物を言ってみる
⑧いのちのない「砂」の悲しさよ
さらさらと握ると指の間から落ちる
⑨しっとりと
涙を吸った「砂の玉」
涙は重いものなんだな
⑩大という字を百あまり
「砂」に書き
死ぬことを止めて帰って来ました
《巻頭》の、
歌集の印象を決定づける大切な役割の一連の歌は、
「泣く」「涙」「錆びたピストル」「墓」「悲しさ」「死ぬ」
などの言葉が列挙されており、
かなり大きな衝撃を受ける内容になっています。
啄木の作家人生が、
どれほどの苦悩に満ちていたのかが想像できますね。
啄木の内面
⇩
自己憐憫、苦悩、絶望感、孤独感、空虚感
⇩
啄木の人生
「砂」は、啄木の人生を暗示していることから、
⇩
(ほんのわずかな一握りの砂)に込められた意味
取り立てるほどの成果もない私の人生
または、
取るに足らないささいな私の命
『一握の「砂」』という歌集の題名からは、
啄木の悲しい思いが、痛いほど伝わってくるのです。
🎹短歌『初恋』が、表現していることとは
『初恋』は、
巻頭の一連の短歌の中にあることから、
単なる「初恋の思い出」として詠んだのではないことは、明らかですね。
6首目の『初恋』の2首前と、1首前の短歌を、
もう一度、合わせて見てみましょう。
この3首には、
「砂山」という言葉が、共通して使われています。
それには、どのような意味があるのでしょうか。
ひどく錆びたピストルが出た
「砂山の砂」を指でもって
掘っていたときに
「砂山」から、ピストルがでました。
次の歌にどのようにつながるでしょうか。
ある一晩に
嵐が来て築いたこの「砂山」は
何の墓かなあ
「ピストルが出た砂山」は、何かのお墓です。
そして、これが、
次の歌『初恋』に、つながっていくのです。
「砂山の砂」に腹這い
初恋のいたみを遠く
思い出す日
つまり、
『初恋』の「砂山」とは、
「ピストルが出た墓」
ということが、わかります。
「ピストルが出た墓に腹這いになって」
初恋のいたみを思い出していることになり、
ここにも、啄木の
強い自己憐憫、苦悩、孤独感、空虚感、絶望感が
込められていることがわかります。
🎼石川啄木の初恋
石川啄木は、初恋の人と結婚しました。(1905(明治38)年)
お互いに淡い恋心を抱いたのは、結婚の6年前で、
「初恋」でした。
それから、お相手の方の猛アタックから実った結婚でした。
結婚後は、
妻となった「初恋」の方は、
啄木が26歳で若くして亡くなるまで、
生活苦と、啄木が繰り返す病に苦労に苦労を重ね、
啄木が亡くなった翌年、後を追うように亡くなりました。
🎼【日本歌曲】『初恋』を歌で表現しましょう
短歌『初恋』に曲が付けられ、【日本歌曲】になりました。
啄木の短歌に付けられた【日本歌曲】の中では、
最も有名な歌曲です。
🎹歌詞としての言葉の繰り返しや、感嘆詞の付け足し
日本歌曲『初恋』が作曲されるときに、
歌詞は、短歌そのままではなく、
言葉の繰り返しや、感嘆詞の付け足しがありました。
※赤字の部分と、短歌全体もしくは半分。
砂山の砂に
砂に腹這(はらば)い
初恋のいたみを
遠くおもいいずる日
ーーーーーーーーーーーーーー
↓ここから短歌の半分繰り返し
初恋のいたみを
遠く遠く
あぁ あぁ
おもいいずる日
ーーーーーーーーーーーーー
↓ここから短歌の全体繰り返し
砂山の砂に
砂に腹這(はらば)い
初恋のいたみを
遠くおもいいずる日
曲の始まりの短いフレーズの間に、
「砂山の砂に 砂に腹這(はらば)い」と、
「砂」の単語を3回繰り返して強調しています。
「砂」とは、
啄木の内面である自己憐憫、苦悩、絶望感、孤独感、空虚感などに満ちた
啄木の人生を表す言葉でしたね。
「砂」という言葉を繰り返すことで、
今の苦しみと、
過去の幸せな「初恋の思い出」との落差を、
表現しているのではないでしょうか。
短歌の半分繰り返しの部分で、
「遠く」が、
「遠く 遠く」と繰り返されることで、
あの幸せは、もう手が届かないくらい
遠くに行ってしまったかのように感じられます。
そして感嘆詞「あぁ」という嘆きの表現で、
「幸せが遠くへ行ってしまったこと」が、
さらに強調されるのです。
🎹日本歌曲『初恋』の作曲者
作曲者は、
越谷(こしたに)達之助(1909-1982)。
作曲家・ピアニスト・詩人・俳優・音楽教師など、多方面で活躍しました。
日本歌曲『初恋』は、
歌曲集『啄木によせて歌える』
(昭和13(1938)年発表)の第一曲目に収録されています。
🎹日本歌曲『初恋』曲調の特徴
♫ 短い曲の間に、
(ピアノ伴奏付きで見開き1ページ分)
拍子が何度も変わりながら進行することで、
心の揺れを表しています。
※4/5(4分の5)拍子→4/4→4/3→4/4→4/5
♫ 明るさも憂いも感じられるゆったりしたメロディー
♫ なめらかに心地良く流れるピアノ伴奏
これらの特徴を持った曲調によって、
啄木の短歌に込められた
強い己憐憫、苦悩、絶望感、孤独感、空虚感が、和らぎ、
純粋に、若者の甘く切ない「初恋の思い出」
を歌っているように聴こえてきます。
「出会った頃は幸せだった」
と、思い返している
啄木の穏やかな顔が浮かぶような曲調です。
石川啄木は、
日本歌曲『初恋』が作曲されたときには、
既にお亡くなりになっていたので、この曲を聴くことはありませんでした。
ですが、もしも、聴いていたとすれば、
啄木の苦悩は、ほんの一瞬でも、
救われたことでしょう。
🎼『初恋』の《女声合唱曲》を委嘱・初演!
『初恋』は、独唱曲として作曲されていますが、
当音楽教室代表で、私の父でもある梅谷邦彦が、総監督・指揮を務めていた、
女声合唱団カナリア・コーラスの
「創立40周年記念コンサート(2007年)」において、
作曲家の岩河三郎先生に、
《女声合唱曲》としての編曲を委嘱し、初演しました。
『初恋』の瑞々しいメロディーが、
《合唱》として幾重にも声が重なることで、
心の奥まで満たされる、
深みのある音色となって、優しく包んでくれるかのようです。
また、
この情緒豊かな美しい【日本歌曲】
『初恋』が、《合唱曲》になったことで、
幅広く一般的に、
多くの人たちが歌える機会が増えたことを、
大変嬉しく思っています。

《熱き心を歌声にのせて》
女声合唱のための「四つの抒情歌②」より「初恋」
(女声合唱曲としての委嘱作品 /初演 )
編曲 岩河三郎
作詩 / 石川啄木 作曲 / 越谷達之助
開催日:2007年9月16日
会 場:吹田市文化会館〈メイシアター〉
中ホール
指 揮:梅谷邦彦
ピアノ:梅谷陽子
合 唱:カナリア・コーラス
🎼【日本歌曲】を代表する名曲『初恋』ご一緒に歌いましょう!
啄木の深い深い内面を映し出した
【日本歌曲】を代表する名曲『初恋』。
情緒豊かで美しい短歌とメロディーを堪能しながら、
当教室でご一緒に、歌いませんか。
前回のコラムでは、
『初恋』をはじめ、【日本歌曲】を表現することが難しいわけ、について、
「【日本歌曲】とは何か」と、
「日本語の特徴について、その難しさと美しさ」
という観点から、お話しています。
ご興味のある方は、是非、ご覧ください。
今回のコラムにもお付き合いいただき、
ありがとうございました。
次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も
よろしくお願いします。
梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪