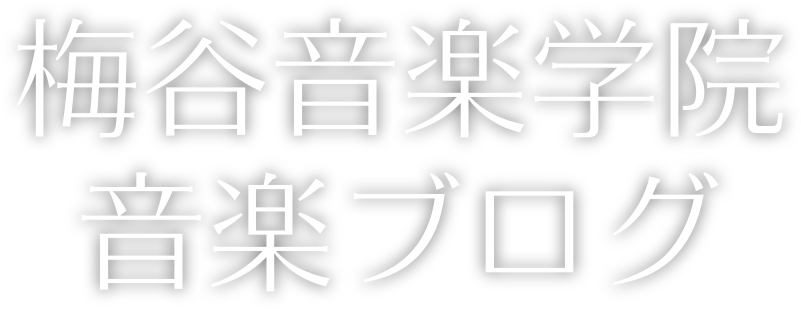🎼『初恋』は、必ず、歌う必要がある名曲です。
【日本歌曲】『初恋』は、
一般的には、あまり知られていないかもしれませんが、
声楽を学んでいく上では、必ず、歌う必要がある名曲です。
なぜならそれは、
ズバリ!とても難しい曲だからです。
といっても、メロディーやリズムが、
特別に難しいわけではありません。
わかりやすい歌詞に、
1フレーズが短くまとまったメロディー、
ゆったりしたテンポ、
楽譜は伴奏つきでも見開き1ページ分の短い曲です。
では、何が難しいのでしょうか。
それは、
『初恋』は、《 表現すること 》が、とても難しいのです。
この曲を、十分に表現して歌えたら、
相当な実力が付いてきた、と言えるでしょう。
つまり、【日本歌曲】『初恋』は、
表現力をレベルアップする練習には欠かせない曲、と言えるのです。
🎼『初恋』の歌のレッスンの前に
当教室の、大人の声楽科クラスでは、
豊かな表現力が求められる【日本歌曲】『初恋』を、レッスンしています。
『初恋』が作られた背景や、内容を学び、
歌の表現力を、より高めていきましょう。
🎼【日本歌曲】とは何か
【日本歌曲】とは、どのような歌のことでしょうか。
簡単に言えば、
【日本語の詩に曲を付けた歌】で、
その中でも特に、
【明治時代の文明開化より後に、西洋音楽の技法で作曲された歌】
のことです。
日本音楽史に多くの名曲を残した作曲家、
山田耕筰(1886(明治19)-1965(昭和40 )年)は、
【日本歌曲】について、次のように述べています。
▼「日本歌曲に就て」 文:山田耕筰
では歌曲とは何であろうか。
それは言うまでもなく詩歌そのものではない。
さりとてそれは純粋な音楽そのものでもない。
それは詩と音楽が不可離不可分の関係におかれた芸術的な融合体を指すのだ。
それをただ単なる音楽的見地から論ずることも無理であり、
詩的観点からのみ吟味するのも誤りである。
それはもはや詩歌そのものではなく
音楽そのものでもない。
全く新しい【歌曲】という芸術的一形態となるのだ。
『放送文化』
(日本放送協会 第8巻第1号 1953年)掲載
⇩ わかりやすくまとめます。
《 詩に曲を付け、
詩の内容を歌で表現することで、詩と音楽が融合し、
より一層、高度な芸術作品となった曲 》
次に、
【日本歌曲】の名曲をご紹介します。
※スペースの都合上、数多くの名曲の中から、少しだけご紹介します。
▼【日本歌曲】の名曲
滝廉太郎: 作曲
(1879(明治12)-1903(明治36)年)
『花』
(春のうらら~の~すみだ川~)
『荒城の月』
(春こうろうの~花のえん~)
仲田 章: 作曲
(1886(明治19)-1931(昭和6)年)
『早春賦』
(春は名のみの~風の寒さや~)
成田為三: 作曲
(1893(明治26)-1945(昭和20)年)
『浜辺の歌』
(明日~浜辺を~さまよえば~)
山田耕筰: 作曲
(1886(明治19)-1965(昭和40 )年)
『この道』
(この道は~いつか来た道~)
『からたちの花』
(からたちの花が咲いたよ~)
世界の国々にも【歌曲】は、あるのでしょうか。
▼世界の【歌曲】
同じように世界には、
それぞれの母国語の詩に付けられた歌曲があります。
例えば、
【ドイツ歌曲(ドイツリート)】とは、【ドイツ語の詩に曲をつけた歌曲】のことです。
ロマン派文学の詩人、ゲーテ、シラー、ハイネらの詩に感化され、
シューベルト、シューマン、メンデルスゾーン、ブラームスら多くの作曲家が曲を付け、
『野ばら』『魔王』『歌の翼に』など数多くの名曲がうまれました。
🎼【日本歌曲】は難しい!
『初恋』は、
《 表現すること 》がとても難しいのですが、
【日本歌曲】は『初恋』に限らず、
全般的に難しい、と言えます。
その証として、私が通った音楽大学では、
1,2年生で、まず、
【イタリア歌曲】【ドイツ歌曲】を学び、
3年生になってから、ようやく
【日本歌曲】を学び始めます。
これは、オペラのアリアを学び始めるタイミングと同じです。
🎼【日本歌曲】が難しいのは、なぜでしょうか。
日本人が母国語の歌を歌うのに、難しいのは、なぜでしょうか。
その理由は、
母国語である日本語が、難しいからです。
【歌曲】とは、
《 詩に曲を付け、
詩の内容を歌で表現することで、詩と音楽が融合し、
より一層、高度な芸術作品となった曲 》
のことでしたね。
【日本歌曲】を歌うには、
まず、詩を読んで、
作者が伝えたいことを理解することが大切です。
ですが、母国語である日本語が難しいために、
作者の心情・感情を読み取ることが、とても難しいのです。
🎼日本語特有の難しさ=美しさ
日本語の、どのような点が、
詩を読み取ることを難しく感じさせるのでしょうか。
▼日本語が難しいとされる特徴
※【日本歌曲】を表現する場合に関すると思われる点のみ
曖昧な表現の言葉
感情表現が難しい言葉
言葉にしていない行間の部分にある心情
情景を表す擬音語・擬態語の多用
遠回しの伝え方・間接的な表現の文
比喩の多用
このような日本語の特徴は、
日本語を難しくしている要因ではありますが、
それと同時に、
日本語を美しいと感じさせる特徴でもあります。
言葉は、
それぞれの国や地域の文化の表れです。
日本語の難しさと美しさの理由は、日本の文化にあります。
🎼日本文化の特徴・《 和の精神 》で曖昧さを好む
日本語特有の難しさと美しさは、
《人との直接的な対立を避けて、和の精神で接する》
という日本文化の表れです。
日本では、
ストレートなことより控え目で思慮深いこと、
多くを語らず、主張せず、
争わずに場をおさめることが、美徳とされる傾向にあります。
曖昧な表現や、遠まわしの伝え方は、美徳なのです。
▼日本人のコミュニケーション文化
日本人が持つ《 和の精神 》
⇩
曖昧な表現の言葉や、
遠回しの伝え方の文として表現される。
⇩
ハッキリと言葉には出していない言葉の間にある心情をよむ。
言葉の前後の流れから意図を推測する。
日本語は、
日本人の《 和の精神 》からもたらされる
繊細な感受性、美意識を表す独特の言葉として、感覚的表現の言葉になりました。
《 感覚として、感じ取らなければならない 》
のが、日本語です。
この日本語の特徴は、
世界では、
「自分の言いたいことが、相手にハッキリと確実に伝えることが良い」
とされる文化の国が大多数な中で、とても珍しいことです。
例えば、
【イタリア歌曲】や【アメリカフォークソング】など、
多くの外国の歌の詩を読んでみると、
曖昧な表現や、回りくどい言い回しなどは、一切ありません。
伝えたいことを、
シンプルにストレートに、確実に言葉・文に表しています。
シンプルでストレートな詩の言葉・文は、
作詞者の言いたいこと、感情が容易にわかり、
歌うときにも表現しやすく、
聴き手にも伝わりやすくなります。
反対に【日本歌曲】は、
曖昧でハッキリしない間接的な言葉・文を使っているため、
《詩を読み取り、歌で 表現すること 》については、とても難しい、と言えます。
🎼感受性・想像力を、日々、トレーニング
【日本語】が母国語である私たちには、
曖昧な表現から感情を読み取ったり、
言葉に表れていない相手の感情を判断したり、
などの感覚的な能力が、備わっていると言えます。
だからこそ、コミュニケーションが成り立っているのです。
会話でのコミュニケーションでは、
相手の言いたいことや、
感情を察するための判断材料が、言葉以外にもたくさんあります。
例えば、
相手の顔の表情、身振り手振り、体の調子、
その時の相手の状況や周りの状況、
さらには性格や、基本的なものの考え方、以前の行動、などです。
ですが、
詩の内容を読み取る場合はどうでしょうか。
作詞者について、どれほどのことがわかるでしょうか。
会話ではなく、
《【日本歌曲】の詩を読み取る》となると、
ハードルは格段に上がるのです。
作詞者の心情・感情を、
敏感に感じ取るためのトレーニングを、日々、積んでいきましょう!
感じたり、
想像したりすることは、
《生きている》実感となるので
日々が、とても充実したものになってきます。
音楽に触れているときは、もちろん、
食事や散歩、
家族や友人とのふれあいといった
日々の生活の中から、
色々な情味を見出して感じ、
感じたことからさらに、想像をふくらませ、
そして、思考を深めましょう。
そのようにして暮らしてきた日本人の感性が、
日本語として表現されているのです。
🎼表現力も、繊細さ情緒豊かさが求められます
繰り返しになりますが、
【歌曲】とは、
《 詩に曲を付け、
詩の内容を歌で表現することで、詩と音楽が融合し、
より一層、高度な芸術作品となった曲 》
のことです。
歌うときにも同じように、
詩の情緒豊かさと融け合える度合いの
繊細な感受性、美意識を表現する力が求められます。
そのためには、
ただ、声を発するのではなく、
ひとつひとつの言葉に込められた心情を
しっかりと意識して歌うこと、
そして、この曲を歌うことを通して、
何を伝えたいのかを明確にして、声を出しましょう。
🎼『初恋』は難しくも美しい【日本歌曲】を代表する名曲
当教室でレッスンをしている『初恋』は、
声楽家が好んで歌う、
難しくも美しい【日本歌曲】を代表する名曲です。
情緒にあふれ、しっとりとした趣があり、
特に豊かな表現力が求められます。
つぎに、いよいよ、
『初恋』について学んでいきます。
日本歌曲『初恋』が生まれた背景を、
主に、作詞者である石川啄木が歌に込めたものを深堀りします。
日本歌曲『初恋』は、単なる「初恋の思い出」の歌ではなかったのです。
詳しくは、是非、こちらのコラムをご覧ください。
🎼『初恋』の《女声合唱曲》を委嘱・初演!
『初恋』は、独唱曲として作曲されていますが、
当音楽教室代表で、私の父でもある梅谷邦彦が、総監督・指揮を務めていた、
女声合唱団カナリア・コーラスの
「創立40周年記念コンサート(2007年)」において、
作曲家の岩河三郎先生に、
《女声合唱曲》としての編曲を委嘱し、初演しました。
『初恋』の瑞々しいメロディーが、
《合唱》として幾重にも声が重なることで、
心の奥まで満たされる、
深みのある音色となって、優しく包んでくれるかのようです。
また、
この情緒豊かな美しい【日本歌曲】
『初恋』が、《合唱曲》になったことで、
幅広く一般的に、
多くの人たちが歌える機会が増えたことを、
大変嬉しく思っています。

(女声合唱曲としての委嘱作品 / 初演 )
編曲 岩河三郎
作詩 / 石川啄木 作曲 / 越谷達之助
《カナリア・コーラス: 創立40周年記念コンサート》
開催日:2007年9月16日
会 場:吹田市文化会館〈メイシアター〉
中ホール
指 揮:梅谷邦彦
ピアノ:梅谷陽子
合 唱:カナリア・コーラス
🎼日本文化の美意識の結晶!【日本歌曲】をたくさん歌いましょう!
日本文化の美意識の結晶である【日本歌曲】は
情緒豊かで美しい曲が数多くあります。
日本人だからこそ、
共感できる、理解できる【日本歌曲】。
楽しみながら、当教室でご一緒に、たくさん歌いませんか。
今回のコラムにもお付き合いいただき、
ありがとうございました。
次回のコラム『ちいさな感動おおきな感動』も
よろしくお願いいたします。
梅谷音楽学院 講師 IKUKO KUBO (^^♪